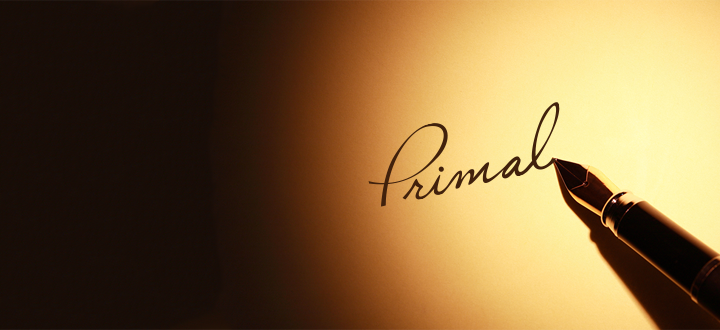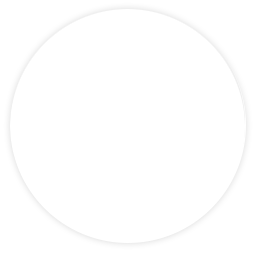事業計画をどう作成するか?(2)
A氏の事業計画書
前回事業計画書の目的について書きました。
しかし、Aさんはなんだか納得いかない様子です。
「でも、あの役員はよく分かってないと思いますよ。口を開けば現場とか執念とかベタベタの話ばかりで、自分が良く分からないもんだから、戦略とか事業計画とかが嫌いなんですよ。」
Aさんは、自分の書いた事業計画書に少なからず自負があるようです。
ではどのようにして事業計画を作成したのか聞いてみると…。
「僕は休みの日も使って、事業計画について書かれた本を5冊ぐらい読破しました。大体書いてあることは似ていたので、どの本にも共通している項目、さらに自分で重要だと思った項目を書き出し、それに沿って書いていきました。だから、事業計画の要諦は把握している自信があります。」
という答えでした。
確かに、Aさんは事業計画を書くに当たって、十分勉強してのぞんだようです。
書くべき項目としては、リストを見せていただきましたが、事業の目的、経営チームの紹介から始まり、事業シュミレーション、コンティンジェンシープランの作成まで、20項目近くありました。実物も、20項目すべてについて触れられているためか、60ページ近くある超大作です。
内容は説得力、納得力が必要
しかし、実際に読んでみると、次の点から腹に落ちてこないのです。
- 内容が多すぎて、全容を把握するのが難しい。
- 何について話をしているのか?前後のつながりがよく分からないところがある。
- 全部を読み終わっても、現実味があるように感じられない。
前回事業計画は、自分でも使える必要があると申し上げましたが、次の段階では当然周りのひと、ステークホルダーを説得できる内容でなければなりません。そういう説得力や納得性が欠けてしまっているのです。
それはなぜなのでしょうか?
チェックリスト症候群
これがチェックリスト症候群と呼ばれる、多少なりとも事業計画の書き方を勉強したり、書きなれたりした人に見られがちな症状です。
確かに、MECEなのですが、この症状が出てしまうと、本人は一生懸命に完璧なものを作ったつもりでも話を聞く側、提案を受ける側は納得しないし、ひどい時には、途中で眠ったり、違う作業をはじめたりします。
また、これらの事業計画書は自分で読み返して普段の仕事の工程表としては使われません。なんだか、普段の実務とかけ離れているような気がするし、なにしろ長すぎるのです。 自分でも読みたくないものは他人も読みたくないはずです。
では、具体的にAさんのなにがいけなかったのでしょうか?
タグ: チェックリスト, 事業計画, 症候群, 計画書