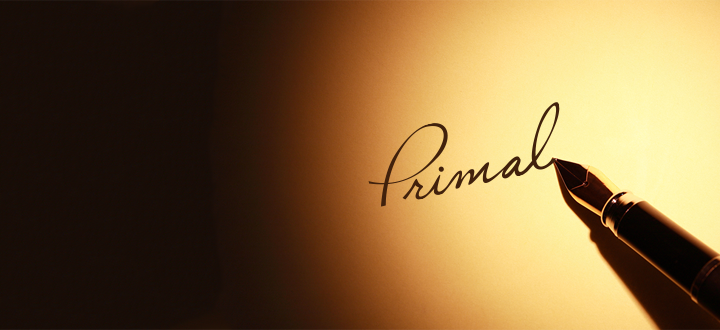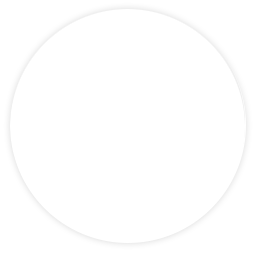事業計画をどう作成するか?(3)
チェックリスト症候群の最大の欠点
Nさんは、
「大体書いてあることは似ていたので、どの本にも共通している項目、さらに自分で重要だと思った項目を書き出し、パワーポイントの表題にしました。その後、それを埋めていきました。」
と話しています。
実はここに大きな落とし穴があったのです。
この手法、前回チェックリスト症候群と呼んだ手法の最大の欠点は、ひとつの項目をきちんと書くこと、空いている項目を埋めることにどうしても意識が集中してしまい、項目ごとのつながりが希薄になってしまうところです。つまり、一項目一項目はしっかり書かれているのですが、前のページと次のページの連関が分かりにくく、話の筋がわかりにくくなりがちなのです。
それとは裏返しなのですが、一項目一項目をしっかり書きすぎることにより、 詳細に複雑な分析をおこなってしまうことになり、
- 事業計画に筋、ストーリーがないので頭に入らない。→理解されない。すぐに忘れられる。
- そもそも、事業計画書全体のボリュームが多くなりすぎる。→最後まで聞いてもらえない。
- 難解な分析をしてしまう。→理解されない。
- 1ページに、多すぎる情報量を盛り込んでしまう。→前を見てもらえない。
などの現象が起こります。
ではどうすればいいのか?
やること × やりかた = お金
それには一度事業計画から贅肉をそぎ落とし、まず骨組みだけをきちんと理解することです。
そして、骨組みとなるのが、
やること × やりかた =お金
というものです。
ちょっと、簡単すぎるように感じられるかもしれませんが、事業計画書においては、この仕組みにつきるといっても過言ではありません。なにしろ、この簡単な仕組みがよくわからない事業計画書が世にあふれているのです。
ここでのポイントは、全体が掛け算になっていることです。
つまり、「やること」と「やり方」がきちんとつながっていて、その結果「お金」を生み出すというところが描けているかが重要なのです。
もう少し具体的に言えば、
- やること:戦略、ビジネスモデルなどが面白いか?新規性あるか?差別化されているか?
- やりかた:アクションプランに実現可能性があるか?実行するためのリソースは十分か?
- お金:損益シュミレーションするとどのくらい儲かるのか?資金繰り表をみると、どのくらいのリスクマネーが必要なのか?
などがわかればいいのです。
例えば、ビジネスモデルと損益計算表とは、実行できる体制やノウハウなどを介してつながりを持っていなければなりません。
関連付けて考える
これぐらい儲かるためには、どの程度の人材がどのくらい必要なのか?
それらの人を雇うために必要なお金は?
そもそも、いくらお金があってもそのような能力をもった人材が採用できるのか?
製品/サービスはその人たちが売りにいきさえすればいいように差別化されているのか?
などなど、考えねばならないことが、次から次へと出てくるはずです。
そして、このように関連付けて考えることこそが、使える自分のための事業計画書作成へとつながるのです。
タグ: 事業計画, 計画書