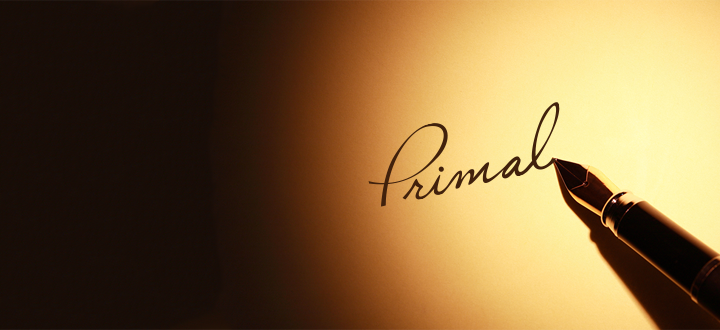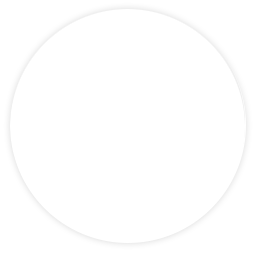映像コンテンツ配信市場はブレイクするのか?(1)
音楽配信市場は急速に拡大している。着うたフル®、アップル社のi-tunesミュージックストア、レーベルゲート社のMoraとビジネス的にも成功といえるものが増えてきた。
成功しつつある音楽配信市場と映像コンテンツ配信市場の比較
レコード協会によると、06年1月?6月で247億円、年間では500億円相当の市場規模になってきている。
一方で、映像コンテンツ配信市場は、USEN社のGyaoの登場、Yahoo!動画のコンテンツ大幅拡充などにより、利用数自体は大幅に上昇しているが、まだまだビジネス的に成り立つ状況ではない。
USENのGyao事業の赤字額は約80億円(売上高は20億円強、06年8月期、数値は2006/10/31日本経済新聞朝刊による)に達している。また、映像コンテンツ配信市場全体の規模も、292億円(デジタルコンテンツ白書2006による)に留まっている。
音楽配信と映像コンテンツ配信はコンテンツ配信という意味では同じであるが、上記の違いは一体どこから生まれるのであろうか。
音楽配信と映像コンテンツ配信
この問題を考える上で、二つの視点から考えてみたい。一つは、流通ルートを変えるに値する「付加価値を提供できるか」どうか?という視点である。
配信サービスは既存のコンテンツサービスからのシフトによる代替的サービスである。音楽配信と映像コンテンツ配信は、「通信を利用し、携帯やPCにコンテンツを送り届け、保存・再生するもの」であるが、これはCD・DVD・テレビなどと比較し、流通ルートが変わったにすぎないともとれる。ヒトは、今までの習慣を変えるには相当の理由が必要になってくる。
もう一つ、実務の現場では見過ごされてしまいがちな視点でもあるのだが、既存の方法と比較して「劣っている点」があるか、それはどの程度重要でどのくらい劣っているのか、という点である。「劣っている点」は、代替的市場においては、事業展開上の阻害要因=ノックアウトファクターとなりやすく、これをクリアすることが成功のカギとなるケースも多い。
つまり、音楽配信が成功しているのは、現在のインターネット配信のインフラ・市場環境において、
- 「劣っている点」が少ない
- 「付加価値」が提供されている
ことにより、映像コンテンツ配信と比較してうまくいっているのではないか、と考えられる。
既存サービスと音楽配信サービスとの比較
既存のサービス(ここでは、CD、DVD、テレビ等)からスイッチするには、需要側=ユーザー、供給側=コンテンツプロバイダ双方が納得する必要がある。映像コンテンツ配信と比較するため、まず、ユーザー側における音楽配信についての付加価値、劣っている点を考えてみる。
音楽配信の付加価値としては、
- ネットワークにつながっていればいつでもどこでも音楽を聞ける(特に携帯は便利)
- 品揃えが豊富
- シングルCDを買うより安い値付け
- アルバム曲を1曲づつ購入できる
- ポータブル端末とPCとの連携がスムーズ
- 楽曲管理ソフトが充実し、楽曲管理がしやすい・今までより便利に聞くことができる
- 試聴ができる
- デジタルオーディオプレイヤに多くの曲を入れられる
=今までのように媒体(MDなど)を持ち歩く必要がない
などが考えられる。
携帯電話のみを考えると、着信メロディーとしてフル音源(着うたフル©等)を利用できることや、携帯1台で購入から聴視まですべてが完結することなどもあげられる。
一方、劣っている点としては、
- 音質がCDより低い
- コピーに制約がある
などがあげられる。携帯においては、メモリーできる曲数が少ない、電池を消耗するなどもある。
供給者側(特にレコード会社などコンテンツプロバイダを指す)にとっての付加価値としては、
- 古いタイトルの販売機会が増加する
- コストが低下する(流通コスト、パッケージコスト、媒体コストなど)
- アーティストが直接販売できる
などである。 劣っている点としては、
- CDの売上が減る可能性がある
- 配信用の新たなリソースが必要となる(ヒト、オペレーション)
- サービス品質が低くなる(音が悪くなる)
などがあげられる。流通(配信)事業者にとっては、権利者・レコード会社の実質的な許諾が必要というのもマイナス点としてあげられる。
上記の「付加価値」についてはアメリカの成功事例もあり、「曲がある程度の価格で揃えば売れる」ことは明白となっている。一方、「劣っている点」は実際少し前までノックアウトファクターになっていた。特に供給者側・コンテンツプロバイダーにとってはCDの売上が減る可能性があり、それは、流通(配信)事業者にとっては供給者の許諾が必要、ということになる。
つまり、「販売の許諾がおりない→曲数が増えない、価格が高くなる(CDの売上が減るのならば相応の価格で売りたい)→売れない」という循環となっていたのである。
では、何故このような状況がクリアされた(されつつある)のであろうか?
タグ: コンテンツ, 配信